 |

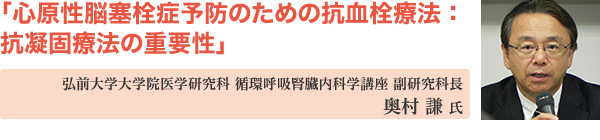
エビデンスの集積と新規薬剤の開発により、心房細動治療は近年、大きな進歩を遂げている。奥村氏は心房細動治療における心原性脳塞栓症予防の重要性と現在の抗血栓療法について述べた。
予後の悪い心原性脳塞栓症とその危険因子としての心房細動
脳梗塞は、ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症の大きく3つの病型に分類される。日本における病型別の罹患率はラクナ梗塞31.9%、アテローム血栓性脳梗塞33.9%、心原性脳塞栓症27%(脳卒中データバンク2009による)で、以前は多かったラクナ梗塞が減少し、食生活の欧米化や高齢化に伴う心房細動の増加により、アテローム血栓性脳梗塞および心原性脳塞栓症が増加傾向にある。予後に関しては、久山町研究(1988~2000年に追跡した集団)において、1年生存率がラクナ梗塞で90%以上、アテローム血栓性脳梗塞も約80%であるのに対し、心原性脳塞栓症は約50%であり、心原性脳塞栓症は非常に予後の悪い脳梗塞であることがわかる。同じく久山町研究では1961年?2000年の観察で心原性脳塞栓症の生存率が改善されていないことも明らかとなっている。 また、心原性脳塞栓症は致死的とならない場合でも重度の機能障害が残ることが多い。
心原性脳塞栓症の大きな要因は、心房細動である。心房細動が脳梗塞の最も重要な危険因子であることが、1990年頃の海外の疫学研究で報告されている。弘前脳卒中・リハビリテーションセンターでの心原性脳塞栓症患者267例における心房細動有病率の検討(2008?2009年)でも、持続性心房細動を有する患者が120例(45%)、発作性心房細動を有する患者が80例(30%)で、実に75%の患者が心房細動を有していた。残り25%の患者も心房細動を検出できなかっただけで、このうち約半数は心房細動を有するものと推測される。
現在、心房細動患者は慢性心房細動患者だけで80万人を超えており、発作性や無自覚の心房細動を含めると100万人以上とみられている。また、2009年に発表された日本循環器学会による疫学調査でも、高齢になればなるほど心房細動有病率が高いことが明らかになっており、今後も患者数・有病率ともに増加すると推定されている(図1)。
前述のとおり、心原性脳塞栓症を発症した患者の予後は非常に悪いことから、心房細動患者においては心原性脳塞栓症の予防が生命予後を改善するうえで最も重要と言える。
 図1 心房細動患者数と有病率の将来予測
図1 心房細動患者数と有病率の将来予測ワルファリンによる心原性脳塞栓症予防とリスク評価スコア
心原性脳塞栓症を予防するには抗血栓療法が有効である。抗血栓療法のなかでは、エビデンスを基に、抗凝固薬であるワルファリンによる治療が行われてきた。ワルファリンの適応とするかどうかの判断に際しては血栓塞栓症のリスク評価が必要となるが、その評価法としてCHADS2スコアが用いられている。CHADS2スコアは、心房細動患者(非弁膜症性心房細動)の脳卒中発症の危険因子である「心不全、高血圧、年齢(75歳以上)、糖尿病、脳卒中/TIAの既往」のそれぞれに点数を付加して、これを合計して血栓塞栓症のリスクを評価する方法である。CHADS2スコアで1点でもリスクが認められれば、ワルファリンの投与が推奨もしくは考慮されてきた。また、これら以外の危険因子では、心筋症、年齢(65歳以上74歳以下)、性別(女性)、冠動脈疾患もしくは甲状腺中毒を有する患者もワルファリンの投与を考慮し、治療が行われてきた。CHADS2スコアに関しては、最近はさらに多項目を含んだスコアリングも提唱されている。
ワルファリンの問題点
ワルファリンはその有効性の一方で、出血性副作用、とくに頭蓋内出血が危惧される薬剤であり、これを最小限に抑えるための管理が非常に難しい薬剤でもある。管理の難しさの要因として、ワルファリンがビタミンKを含む食品の影響を受けることや他の薬剤との相互作用があること、治療において血液凝固能の指標であるPT-INR(プロトロンビン時間国際標準比)を適正閾(一般的にPT-INR=2.0~3.0)に保つ必要があることなどが挙げられる。
PT-INRが適正閾に収まる日数が全診療期間に占める比率をTTR(Time in Therapeutic Range)という指標で評価するが、ワルファリン治療ではTTR は60%以上が望ましいとされている。それに対し、弘前大学など複数の施設において501例を対象に2年間追跡しTTRを解析した研究では、70歳以上(PT-INR=1.6?2.6)では77%であった一方、70歳未満(PT-INR=2.0?3.0)では46%であった(図2)。これはわが国で全国的にみられる傾向であり、ここにもワルファリン療法のひとつの限界があると言える。
 図2 多施設研究における年齢別のTTR
図2 多施設研究における年齢別のTTR血液凝固系における抗凝固薬の作用点と新規抗凝固薬の開発
血液凝固系における作用点からワルファリンの抗凝固作用をみると、ワルファリンは血液凝固系の第II因子、第VII因子、第IX因子、第X因子を減少させることにより凝固活性を抑える。特に、血液凝固系の最も上流の第VII因子への作用が、ワルファリンが脳出血を起こしやすい原因と考えられている。
これに対し、わが国でも2011年3月に発売された直接トロンビン阻害薬のダビガトランや、現在開発中の第Xa因子阻害薬は血液凝固系においてワルファリンより下流の段階に作用するため、脳出血が起こりづらく、さらにこれらの薬剤はPT-INRのコントロールを必要としないなどワルファリンに比べて管理が簡便なため、期待されている。
最後に奥村氏は、「新規抗凝固薬の登場で、わが国の心房細動を原因とする心原性脳塞栓症の予防も新しい時代を迎えた」と現状を総括した上で、今後のさらなる新規抗凝固薬の開発に期待を示し、講演を結んだ。